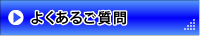1.助成の概要
本助成事業では、特に社会的・学術的課題解決への寄与度を重視し、成果として国際的に評価される質の高い論文や研究成果の創出を期待しています。
2.助成の対象
- 構造・機能材料の研究(例:高強度鋼、軽量合金、複合材料、耐熱材料など、社会基盤や産業競争力の強化に資する研究等)
- 環境・エネルギー材料の研究(例:カーボンニュートラル、資源循環、エネルギー変換・貯蔵に関する材料等)
- その他、先端材料および学際領域の研究
- 派遣助成:過去に当財団の研究助成を受けた者が、海外でその研究成果を発表するための活動費用
- 招聘助成:海外において先進的な研究を行う研究者を招聘し、学会等にて国際交流を行うための活動費用
3.研究助成の対象とならない研究
ただし、知的財産権の確保のための特許化は妨げません。
ただし、申請者が主体的に遂行する研究で、他資金と明確に区分できる場合は対象とします。
4. 助成対象者
① 日本国内にある大学と大学附属研究所、大学共同利用機関法人、高等専門学校、公的研究機関を主たる勤務先とする研究者で、勤務先の所属長(大学の場合は、学部長、学科長以上)から当該研究助成申請の承諾を得ることができる研究者であること。
② 申請テーマに取り組むことが、雇用契約上や職務内容上に支障がない研究者であること。
③ 科研費研究者番号(e-Rad番号)を取得している研究者であること。
④ 研究期間を通して、研究計画の推進に責任を持ち、助成金の管理及び助成期間満了後の報告を確実に行える研究者であること。
なお、研究期間中の所属先の変更は原則認められませんが、新旧両所属先が研究の継続を認め、設備等を含めて研究継続に支障がない場合に限り認めることがあります。また、申請研究者に予期しなかった事情が生じ、研究継続が困難になった場合には、研究を中止し、助成金の返還を求めることがあります。
⑤ 職務専念義務上、外部研究費の受給にかかわる制約が生じない研究者であること。また、他の外部資金とのエフォート率の整合性が確保されていること。
⑥ 当財団の助成に連続して採択されていない研究者であること。
⑦ 当財団に対して、同一年度の複数の応募申請をしていない研究者であること。
⑧ 経済安全保障関連法令に抵触する技術の国外流出に関与していないこと。
⑨ 反社会的勢力との関与がないこと
5.助成金額と件数
① 研究助成:300万円/件(間接経費10%を含む)
② 国際交流等助成(派遣):75万円/件(間接経費10%を含む)
③ 国際交流等助成(招聘):75万円/件(間接経費10%を含む)
※ ②、③ の対象国が別紙記載のアジア圏22か国※1の場合については、最大50万円/件(間接経費10%を含む)とする。
① 2025年度・研究助成件数:233名、助成金額合計:6億7330万円
② 2025年度・国際交流等助成件数:26件、助成金額合計:1,816万円
6.助成期間と助成金振込時期
① 助成金は所属機関の指定する銀行口座に振り込みます。また、研究助成については、同一機関で複数の研究者の採択があった場合、まとめて振り込みとなります。
② 研究助成:2026年4月1日から2028年3月31日の2年間
助成金交付時期:2026年7月15日(予定)に交付金額50%、2026年12月15日(予定)に交付額の残り50%
③ 国際交流等助成:2026年4月1日から2027年3月31日の1年間
原則として、渡航1か月前を目途に交付します。
7.助成使途(助成対象経費)
- 助成金交付申請書に記された研究目的を達成するために直接必要な経費
- 補助人件費(研究補助者等の労務対価。申請総額の30%以内とします。)
- 旅費
- 委託費(自施設できない公的機関等への委託実験等)
- 会議費(検討会、学会等参加費等)
- 機械器具費(実験機器、検査機器、分析ソフト等の購入費等)
- 消耗品費
- その他(論文掲載費、特許等出願費、通信費、図書費、学会参加費、印刷製本費、会議費等)
- 間接経費(交付額の10%以内とし、交付額に含まれます。)
- 対象経費として認められないもの
- 申請研究者および共同研究者の人件費
- 海外旅費(研究上必要不可欠と認められる場合は可)
- 汎用性のある機器(コピー機等の複合機、PC、タブレット等周辺機器等)
- 設備の移設費、引越し費用、研究室の内装工事費等、研究に直接必要な経費と認められないもの
- 出張経費(往復航空運賃、移動旅費、現地滞在費、ビザ費用、旅行保険費用、予防接種等)
- 派遣期間に移動日を加えた日数分の日当(所属機関の旅費規程による)
- 学会等参加会議費(諸経費を含む)
- 間接経費(交付額の10%以内)
- 被招聘者にかかる実費(渡航費および滞在費用等)
- 被招聘者への謝金または日当(所属機関の規程による)
- 学会等参加会議費(資料印刷費、その他諸経費を含む)
- 間接経費(交付額の10%以内)
- 申請に際しては、見積書を取得し、附随する工事費や建替えが必要ないかの確認を必ず行ってください。採択後に別途費用が発生することが判明し、本来の研究が十分に行えない場合には、採択を取り消すことがあります。
- 助成期間中に、助成金受領者本人が他の研究機関に異動し、新旧の研究機関同士での移管手続きがスムーズに行われないことが明らかな場合には、返金を求めることがあります。
- 各助成金交付においての間接経費は交付額の10%以内とします。助成額の上限を超えないようご注意ください。間接経費については応募前に各所属機関の担当者様にご確認、ご相談をお願いします。当財団より所属機関へ間接経費の免除をお願いすることはありません。
- 申請時の使途を変更する必要が生じた場合、事前に事務局に相談し、使途変更許可を得てから実施してください。当初申請から大きな変更が生じた場合、選考委員の了解が得られない場合は、採択を取り消す場合がありますので、十分検討して申請してください。
8.応募方法
- 研究者登録(所属機関情報等の基本情報登録)
- 助成申請内容の入力 (研究課題名・助成申請金額等の登録)
- 申請概要(様式1) (PDF形式によるアップロード)
- 研究助成の添付ファイル(各ファイルをアップロード)
※ 当財団の各種助成申請の手続は、Microsoft Edge・Mozilla Firefox・Google Chrome・Apple Safari の各ブラウザの最新版にてご利用ください。
- 申請にあたっては、勤務先の所属機関長(大学の場合は、学部長、学科長以上)からの当該研究助成申請の承諾書(様式17)が必要になります。事前に所属機関長の承諾書について所属機関の担当者様にご確認ください。
- 所属機関単位での応募者数に上限はありません。
- 一度に複数の研究助成を、応募することはできません。ただし、他の申請者の共同研究者として名前が記されることには問題ありません。
- 当財団の助成受領者が連続して応募することはできませんが、他の申請者の共同研究者として名前が記されること自体は問題ありません。
- 書類管理の都合上、財団への持参はお断りします。
- 万一、故意の虚偽記載、同一テーマによる重複申請、あるいは研究倫理上の問題等が認められた場合は、当該申請は無効とし、以降の申請は受けつけられません。
9.選考概要
- 研究助成
- 助成事業の目的・趣旨や募集する研究領域と合致しているか
- 研究の独創性や新規性があるか
- 研究内容の具体的な計画・方法は妥当か、実現可能性があるか
- 成果目標が明確で、達成度を評価する指標が設定されているか
- 研究内容に学術的及び社会的意義と波及効果があるか
- 助成金使途が明確で、費用対効果があるか
- 国際交流等助成(派遣)
- 派遣する国際会議または学会等の社会的評価はあるか
- 発表する研究内容と国際会議または学会等との適合性があるか
- 派遣計画と効果に妥当性、有効性があるか
- 助成金使途が明確で、費用対効果があるか
- 国際交流等助成(招聘)
- 招聘する研究者との交流目的に社会的意義があるか
- 招聘者と参加会議または学会等との適合性があるか
- 招聘計画と効果に妥当性、有効性があるか
- 助成金使途が明確で、費用対効果があるか
- 形式面審査: 応募受付後、12月中に事務局にて形式要件を満たしているかの審査を行います。
- 書類審査 : 形式要件を満たしている申請書について、1月から2月上旬に選考委員による書類審査を行います。
- 選考委員会: 選考委員による評価を踏まえて、2月に開催される選考委員会にて助成金受領候補者を決定します。
- 理事会決議: 3月に開催される理事会にて、助成金受領者を決定します。
- 採否通知 : 4月上旬に採否を電子メールにて、申請者及び所属機関に通知します。
- マイページに登録されたデータに基づいて採択通知を行いますので、異動等あった場合は、当財団のホームページからログインし、マイページの登録データを修正してください。
- 採否の理由についてのご照会には回答致しかねますのでご了承ください。
10.助成金受領者の義務
助成金受領者は、採択通知後、当財団との間で助成金に関する覚書を締結していただきます。助成期間中は、当該覚書と採択された助成金申請書に基づいて研究を実施していただきます。
助成金受領者は、申請書に記載した期間内に研究を完了していただきます。当財団では、研究期間の延長は認めておりません。諸般の事情により期間内に完了できないことが明らかになった場合、または研究を中止した場合には、助成金の受給資格を失い、支払済みの助成金の全額または一部の返還を求める場合があります。未了または中止の可能性が生じた場合は、速やかに事務局までご連絡ください。
助成金受領者は、助成金交付申請書に記載した内容から変更を行う場合、事前に事務局に相談の上、許可された場合は、速やかに助成金使途変更届(様式19)を提出していただきます。
助成金受領者は、研究終了後、研究成果報告書および収支報告書を下記期日までに当財団のホームページからマイページへアップロードして提出していただきます。
- 研究助成
- 中間収支報告(2027年3月31日現在):2027年5月31日
- 研究成果報告書:2028年3月31日
- 収支報告書:2028年6月30日
- 国際交流等助成(派遣)
- 研究成果報告書:助成金受領者の帰国日から3か月以内(最長2027年6月30日迄)
- 収支報告書:助成金受領者の帰国日から3か月以内(同上)
- 国際交流等助成(招聘)
- 研究成果報告書:招聘者の帰国日から3か月以内(最長2027年6月30日迄)
- 収支報告書:招聘者の帰国日から3か月以内(同上)
当該研究成果を発表する際には、当財団から助成を受けた旨をご記載ください。英文の場合は、下記のようなAcknowledgementをお願いいたします。また成果発表については、論文要旨や論文等を当財団のホームページからマイページへアップロードして提出していただきます。
(例)This work was supported by the Iketani Science and Technology Foundation
当財団が主催する研究成果発表会が開催され、参加の要請があった場合は、助成金受領者が参加して、研究の経過または成果の発表をしていただきます。
助成終了後、5年間は当財団からの各種調査等に対して協力していただきます。
11.贈呈式と成果発表会
12.研究成果の取扱い
当財団では、研究成果の公表を、当財団ホームページへ掲載し、また、J-STAGEへの掲載を予定しています。必要に応じて冊子等で紹介を行うことがあります。
- 研究助成の成果に基づいた特許または実用新案の出願に際しては、当財団は権利を主張いたしません。
- 特許または実用新案の出願のため、研究成果報告の公表を留保したい場合はシステム上で公表日を各自設定してください。
- 当財団の助成による研究成果が発表された場合は、論文別刷や著書等のPDFファイルをマイページからアップロードしていただければ幸いです。
13.個人情報の取扱い
14.問合せ先
info@iketani-zaidan.or.jp